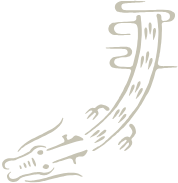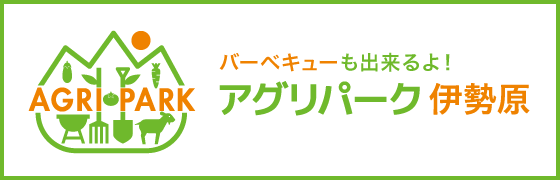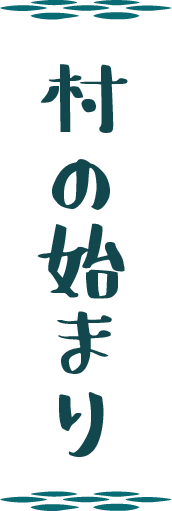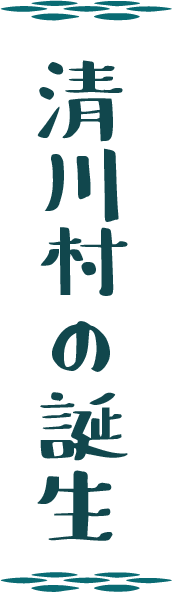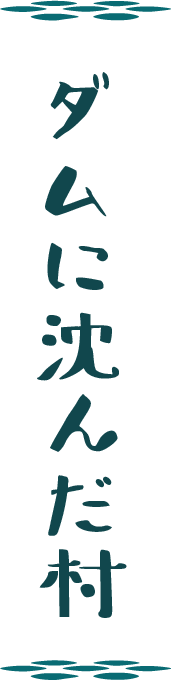青龍の
棲む里
棲む里
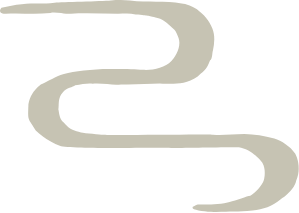
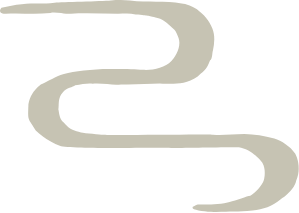
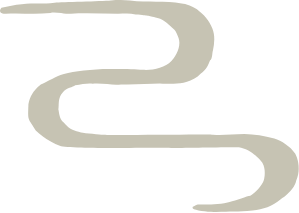
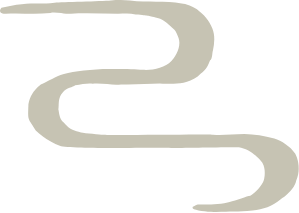
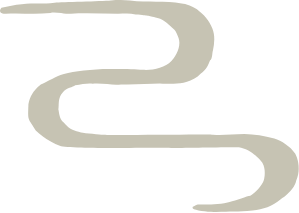
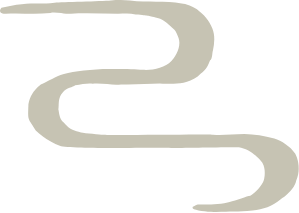
神奈川県唯一の村として歴史を紡ぐ清川村。
旧石器時代の遺跡もあり、昔より豊かな自然の中で
人々の営みが行われてきました。
中世の頃には関東地方を統治していた
北条家の家臣井上氏によって開拓されたと言われており、
永禄12年(1569年)甲斐の武田信玄軍と
小田原の北条氏康軍が現在の愛甲郡愛川町三増で
合戦を繰り広げた際に戦場となり、敗れた北条軍が
清川村の経ヶ岳山頂に向かったという伝えも残っています。
B.C
~1569
~1569
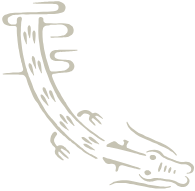


元々「煤ヶ谷村(すすがや)」と
「宮ケ瀬村(みやがせ)」に分かれていましたが、
昭和31年合併し、「清川村」が誕生しました。
新しい村名となった「清川」の由縁は、
「山に生きる村として~川の自然の清らかさを
とこしえに保ち~(一部省略)」という
理想を込めて名付けられました。
当時は、林業を中心として
炭焼きや養蚕などが主な村の産業でした。
1956

都市部の水需要の確保の為、
昭和44年に宮ヶ瀬地区に多目的ダムを
建設する計画が発表されました。
旧宮ヶ瀬村の殆どがダムの湖底に沈んでしまう事になり、
村民は様々な検討を行い昭和56年、
工事に関する調印式が行われました。
平成12年12月、建設計画発表から31年の歳月をかけ、
神奈川県の水瓶として、「宮ケ瀬ダム」が完成。
人口湖は「宮ヶ瀬湖」として、家族がふれあえる空間として
整備が進められ現在に至ります。

1969
~2000
~2000